子育ての目標は子どもの自立です。
とはいっても、
「うちの子はなんだか頼りなくって・・」
「私がいないと何もできないの・・」
など、子離れできない理由を感じているお母さんは多いのではないでしょうか。
私もかつてはそう思っていましたが、子どもから言われた一言をきっかけに考え方を変えました。
今に至る経緯をお伝えします。
子離れできない原因は親の私にあった

私は母や祖母にやや放任主義で育てられたため、自分で言うのもなんですが、早くから精神的に自立していました。
8歳のときに虫歯になって歯医者通いをしましたが、仕事の母に代わって祖母が着いてきてくれたのは初回のみで、以後はひとりで通院。(受付の人も先生もびっくりしていた)
「自分で決めなさい」「それくらいひとりでやりなさい」と言われて育ち、気が付いたら進路も結婚も何もかも一切の相談なく、すべて自分だけで決めるようになっていました。
周りの同級生は親に相談したり悩みを打ち明けていると知ったとき、親に頼れなかった私は心の奥底で寂しかったのだと気づき、同じ思いを自分の子どもにはさせたくないと思いました。
でも・・
愛情いっぱいに手塩をかけて育てていたつもりの娘からある日、「ママが私を心配して言ってくれているのはわかる。でも自分でやってみて失敗させてほしい。」と言われました。
娘が中学生のときの話です。
自己肯定感が低くかった私は、娘には自己肯定感が高くあってほしいと願い、失敗しても「大丈夫だよ」「これも経験だよ」と前向きに励ましていましたが、娘からすればそもそも手痛い失敗をした経験が積めていないと感じていたということです。
私はいつのまにか、自分の心配を子どもに押し付けてつい先回りしたり、余計に手を貸してしまっていたようでした。
子離れできない原因には夫婦関係も
子どもが生まれてからずっと旦那との折り合いが悪く、一時期はその存在を無視するほど冷めきっていました。
娘の前ではそんな素振りを見せていませんでしたが、思春期に入ると娘のほうから父親の愚痴を言うようになり、娘の話を聞きながら私は同志を得たような気持ちになっていました。
しかしそれも、いずれ娘が就職や結婚などで家を離れてしまえば、分かち合える人がいなくなってしまう。
そんな不安から、「この子には私がいなくては」と思える状況を、私の勝手で作り出していたのかもしれません。
実際に、夫婦関係の悩みが少しずつ解決に向かい出すと、以前ほど娘が家を出ていくことに不安がなくなりました。(寂しさはあるけど)
もし、私の気持ちがわかる!という場合は、お子さんとの関係を見直すのと同時に、旦那さんとの関係も考えてみてください。
\夫婦関係の悩みを改善できた方法はこちら/
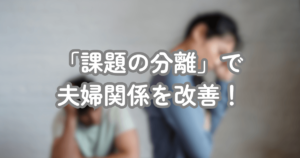
子離れできない親子の末路
子離れできない親子の末路は「共依存」です。
子どもが選んだ友人、恋人、進学先、結婚相手に対し、不安や心配から良かれと思って「付き合うのをやめたら?」「もっといい会社があるかも」とアドバイスをし、子どもも「お母さんがいうなら」と何の疑いもなく受け入れてしまう。
もしくは、何を言っても反対されるからと無気力になり、母親の言いなりになってしまう。
子どもが頼りない(と感じる)ことを理由に子離れを拒み続けるのは、「将来この子はどうなってしまうのだろう」と不安を感じながらも、現状を変えずにいるほうが居心地が良いからなのかもしれません。
そして子どもも、親ありきの自分の人生に違和感を抱きながらも、共依存状態が長く続けば続くほど、そこから抜け出せなくなります。
特に一人っ子は親子関係が濃密になりやすく、共依存に陥りやすいのだとか。
「失敗させてほしい」という娘の言葉を無視していたら、私たちもいずれはそうなっていたのかもしれません。
困っていると察して手を差し伸べるのはやめた

今までの私は、娘が困り事を抱えていると察した瞬間、「何かあった?」とすぐに声をかけていました。
・・いえ、娘が何とかしてみようと思う前の段階で、「きっとこんなことに困るだろうから」と先に手を出していたこともあったのかもしれません。
娘から「失敗させてほしい」と言われたときはやっぱりショックでしたが、自分を変えなければ娘の人生を台無しにしてしまうと気づくきっかけにもなりました。
それから、私は娘の様子を察して声をかけすぎるのをやめるようになりました。
子どもの真の自立とは
世間一般的には、子どもの自立は「何でも自分で決めていける強さを養う」こととされます。
でもこの言葉のニュアンスには、自分で決めたら最後まで自分で抱えて責任を負うという意味合いが含まれている気がします。
私は何でも自分で決めて生きてきましたが、人に頼れず、生きづらさを抱えてきました。
子どもが養う何でも決めていける強さには、自分では解決できない困り事を抱えたときに、自ら周りに相談できる柔軟さもなくてはならないと思います。
子離れを始めてみてわかったこと
高校生の娘が友達と連れ立って、札幌まである歌手のコンサートへ出かけたときのこと。
帰りは遅くなるので旦那が駅まで迎えに行くことになっていましたが、行きは友達と電車に乗ります。
しかも会場は今まで行ったことがない場所で、地下鉄に乗ったこともなく、夜道も不安です。
「行きも旦那が連れて行ったほうがいいのでは?」と過保護の私が口を出しそうになりましたが、ぐっと堪えて見守ることに。
娘自身が考え、もしそうしたいなら、娘から旦那にお願いしたほうがいいと思えたからです。
結果的には、道中は終始娘が率先して電車や地下鉄の時間を調べ、会場への行き方も道を歩いていた人に尋ねて解決したそうです。
普段はぼーっとして何も考えてなさそうなのに、意外としっかりしているのだなと驚く出来事でした。
子離れの現在地
親としてこれは外せないと思うルールがあり、それを守ってほしい理由を時間をかけて娘と話し合っています。
例えば、夜間の外出では駅までの親の出迎えは、大学生の現在でも必須にしています。
一方で、バイト先選びやアルコールを伴う場への出席などは娘に一任しています。
これは、どうするかを自分で考えられるだけの経験や知恵を、娘が備えていると親として判断できるからで、そのように娘にも伝えています。
中学生のときに私に「失敗させてほしい」と言った娘は、今は私からの言葉に信頼されていると感じているようです。
子どもが親離れするには親の自立も必要

娘が中学生のときに子離れを強く意識し始め、高校生、大学生と徐々に段階を上げ、社会人まであともう少しというところまで辿り着きました。
子どもの自立を願って子離れをしながら、同時に私自身も自立しなければと思うようになっています。
私にとって娘は、世界でたったひとり、自分の命よりも大切な存在です。
そして、娘を産んで育てたことで、自分が長く苦しんだ生きにくさの原因に気づき、生き直しのきっかけを与えてくれました。
そんな娘に、これから私ができるのは「ママっていつも楽しそうだね」と思ってもらうこと。
「そうだよ。ママは自分ひとりで楽しめるから、あなたは自由に羽ばたいていいんだよ」
そう言えるように、更年期の体調管理や趣味、社会とのつながりなどに自分の意識や時間をシフトしていきます。

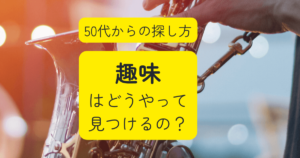
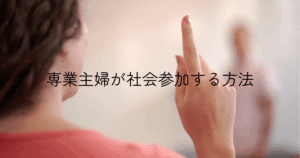
おわりに
娘に「失敗させてほしい」と言われる前になぜ気づけなかったのかと、今でも悔むことがあります。
それでも「失敗させてほしい」と私に言えるだけの信頼を、娘が持っていてくれていたことが幸いだったとも感じました。
今後も続く子離れの階段を、一歩ずつ上がっていこうと思います。
ブログを読んでくださりありがとうございます。
バナーを押すと、ブログ村の「IN」のランキングに1票が入る仕組みになっています。
応援クリックしていただけると励みになります。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
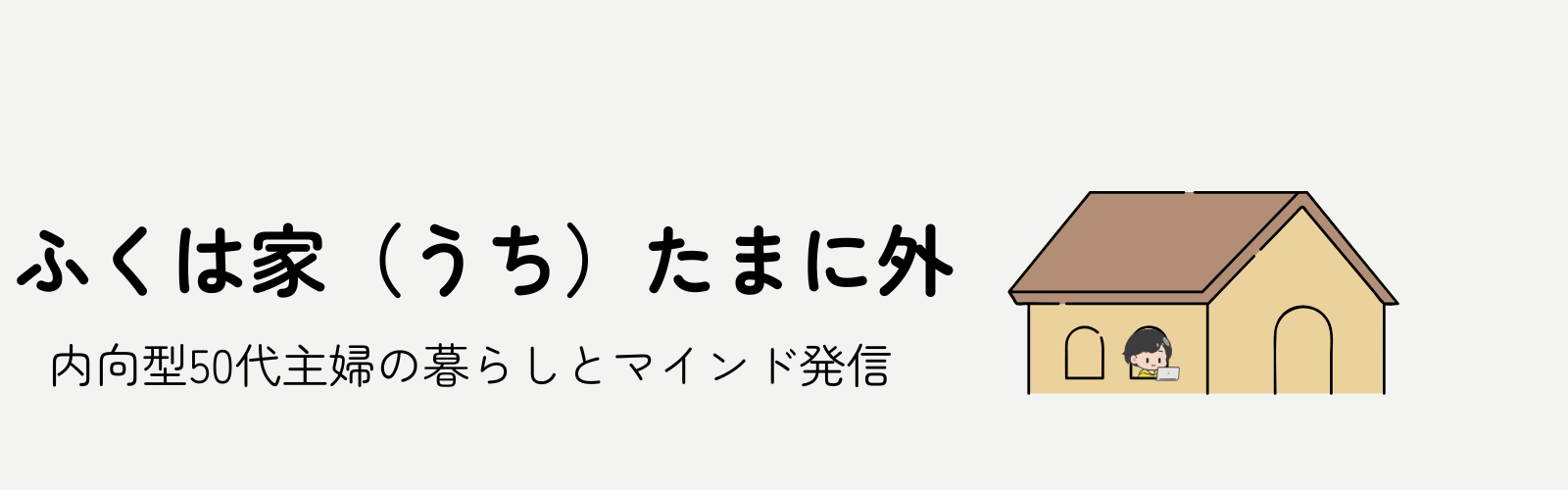


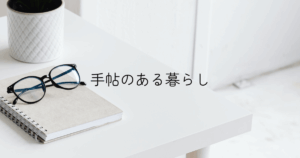
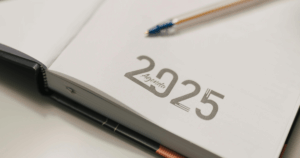
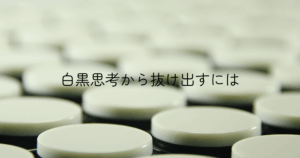
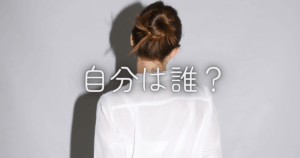
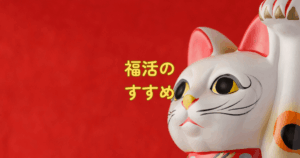
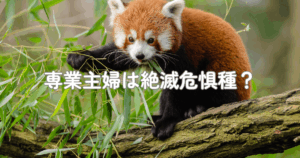

コメント