内向型外向型、MBTIなど、自分を知るためのツールは世の中にたくさんあります。
私は内向型のINFJと自分の「型」がわかったことで、生きづらさに気づくきっかけになり、診断結果にはとてもしっくりときていますが、もっと「核」の部分が知りたいと思うようにもなりました。
本当の自分を知るために、私が始めたことを紹介します。


「本当の自分がわからない」はどうして起こる?

50代が近づくにつれ、自分はどう生きたいのか、なにがしたいのかと考えてみても、自分のことなのによくわかりませんでした。
そうかと思ったら、「私はこう思う」と口にして自ら行動を選んでいるのに、後からモヤモヤする感覚に陥ることもあります。
本当は自分がどう思っているのかわからなくなるのは、一般的には次のような理由が考えられるのだそう。
- 他人を優先したり他人の期待に応えようとしすぎている
- 自分に自信がない
- 失敗するのが怖い
私自身、どれも当てはまることばかりで、本当の自分がよくわからなくなってしまうのには、ある意味でちゃんと理由があったのだと頷けました。
“自分史の作成”が気づきの大きなきっかけに
私が自分史を作成し始めたのは、自分のこれからの人生をどう生きるか、それを見つめ直す方法のひとつとして紹介されていたからですが、結果的に自分を知るためのとりかかりとしてとても役立ちました。
過去から現在までの経験を振り返る作業は、自分の価値観や行動パターンの可視化につながり、思考の癖に気づけたからです。
本当の意味で自分を理解する必要があると、強く感じる大きなきっかけとなりました。
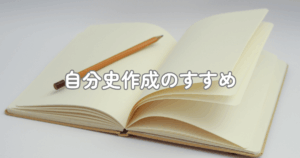
思考の癖とは
今の自分は、過去に起こった出来事から自分なりに学習して、自分なりのルールを無意識に決めています。
失敗しないように、自分を否定しないように…。
この無意識のルールこそが思考の癖です。
たとえば、私は人から「どうしてこれがほしいとわかったの?」とか「~してくれてたらいいなと思うことをしてくれているからすごい!」と言われることがあります。
これは、先回りができていないと自分の存在価値がないと感じてしまう、私の思考の癖からの行動でした。
長年に沁みついた思考の癖は簡単には変えられませんが、パターン化した自動思考に対して「もしかしたら今、癖が出ているのかも」と思えるようになるだけでも少しずつ自分が変わります。
自分を知るためにしていること
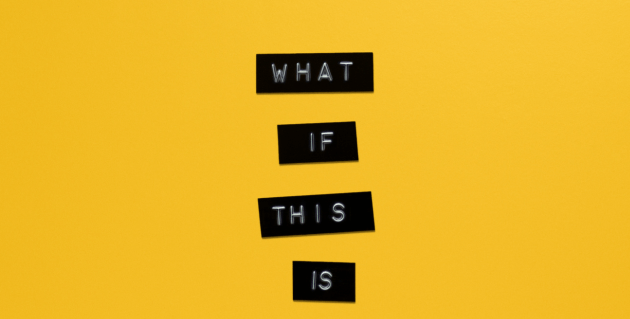
自分を知る方法として、好きな食べ物や得意なこと、長所や短所などを書き出す作業があります。
やってみたものの、私には自分という大まかな形がぼんやりと見えてくるだけ。
それよりも、好きな食べ物はどこが好きなのか、これを得意だと思えるように私はなにをした?といった問いかけを自分にしてみると、自分の「核」に行き着く手ごたえがありました。
なぜ?どうして?より「なに」
自分に問いかけるときに、なぜ?どうして?と聞いてしまうと、私は自分が責められるような気持ちになったり、納得できるような答えを見つけようとしてしまう傾向がありました。
それよりも、「なに」に置き換えるとすんなりと素直な気持ちになれました。
「どうしてイライラしているの?」よりも「なにがイライラさせているの?」と聞いたほうが、自分を取り巻く環境を含めて冷静に考えられて、イライラしている(させている)原因が見つけやすくなりました。
\Yahoo!ニュースに上がっていました!/
感情を言語化する重要性
問いかけをしても、自分の感情を上手く伝えられないと落ち込んだり、苦しくなったりします。
この気持ちに名前がほしいと思ったことは、過去に何度もありました。
そんな私は、読書を始めてから語彙力が増え、感情を言語化できるようになりつつあります。
問いかけによって自分の奥深くにある感情を探り、その気持ちに名前をつけられるようになると、得体のしれない感情にコントロールされることが少なくなって、思考が整理しやすくなります。
そうすると、他人に対して自分の思いを伝えられるようになり、ストレスが減りました。
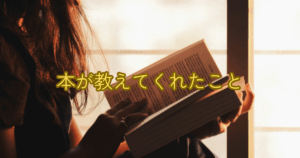
問いかけは感情を受け入れるステップ
「寂しい」「悲しい」「苦しい」など自然と沸き上がってくる感情を、「忙しい親に甘えてはいけない」「これくらい耐えられなくては上手くなれない」「社会人なら我慢して当然だ」などの思考で蓋をする。
そんなことを繰り返していた私は、ネガティブな感情を抱く弱い自分を認められず、大切にできないまま、大人になっていました。
自分を閉じることで、波風が立たない生き方をしてきたけれど、行き場のなくなった感情はずっと心の奥底に居座り続けていて、きっとそれこそが本当の私なのだと思うようになりました。
旦那にイライラした、ニュースを見てつらくなったなど、気持ちが大きく揺れたとき、その揺れをぐっと押さえつけてなきものにしていましたが、「なにがあなたをつらくさせるの?」「つらくならないためにはなにをすればいい?」そう自分へ問いかけることで、少なくても自分の感情を自分が受け入れることはできます。
感情にちゃんと行き場ができるし、自己理解が深まっていく感覚があります。
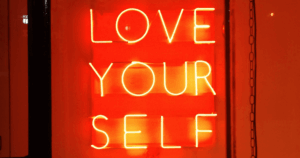
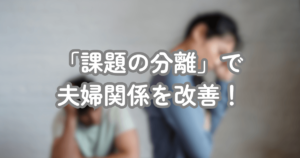
自分を知ることは自分をうまくコントロールする方法を得ること
「なに」を主軸にした自分への問いかけは、今の感情を受け入れながら、今よりも少し先の自分の生き方や考え方を明るくする力になります。
感情に捉われすぎず、自分ができること、できそうなことに意識が向くからです。
「自分ができないのはなぜなんだろう?」と考えてしまうと、ひたすら自分を責めてしまうことがありましたが、「自分にできないことやできることはなんだろう?」と問いかけると、まったく見える景色が違いました。
おわりに
本当の自分を知ることを始めてから、他人との関係が上手くいくようになりました。
その理由のひとつは、相手もきっと自分をよく知らないで困っていると思うようになったから。
「なぜ?」「どうして?」を他人ではなく、自分に向けてみることで、一歩ずつ自分の「核」に近づいている感覚が味わえると思います。
ブログを読んでくださりありがとうございます。
バナーを押すと、ブログ村の「IN」のランキングに1票が入る仕組みになっています。
応援クリックしていただけると励みになります。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
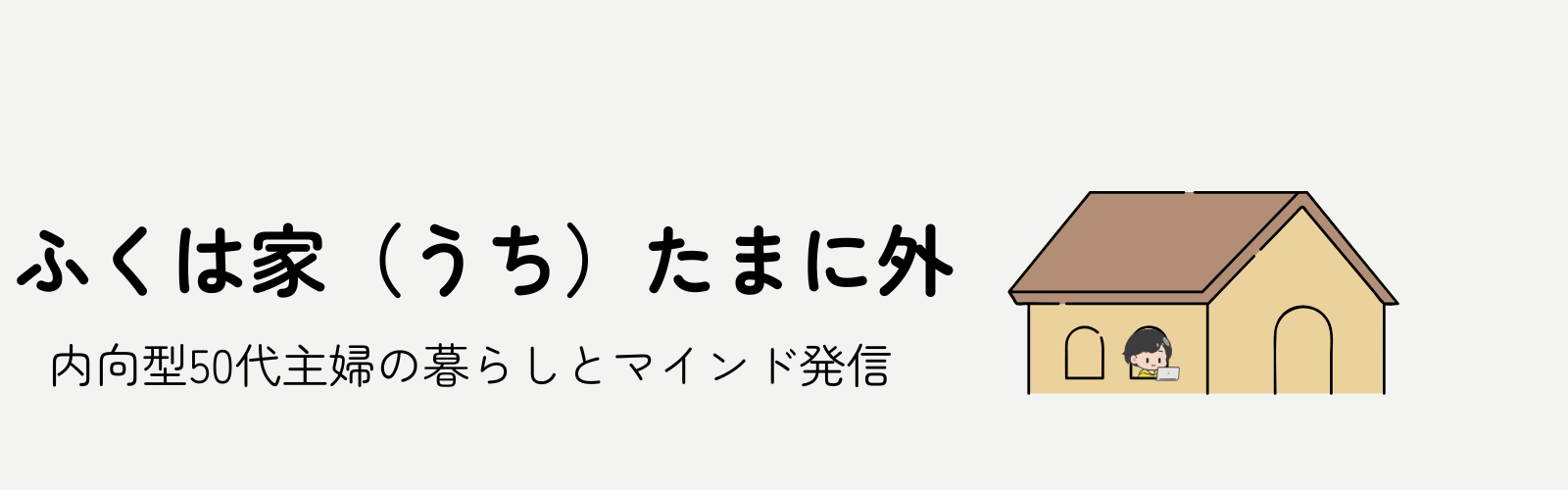



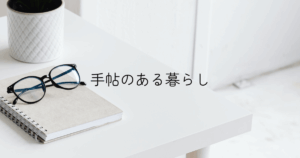
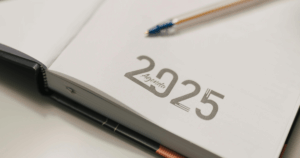
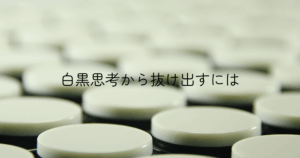
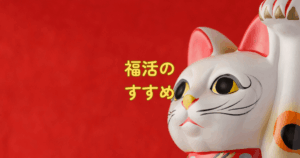
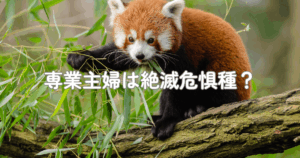

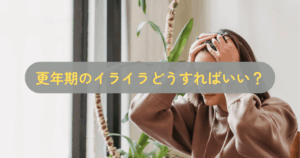
コメント