お中元やお歳暮は、一度贈り始めてしまうと自分からは「やめたい」とはいえず、半ば義務感で続けている人は多いですよね。
最近は物価が上昇し、金銭的に負担を感じていて「そろそろやめたいけれど、今やめていいのだろうか」と悩んでいる人も多いでしょう。
我が家は今はどちらもやめています。
人それぞれお中元やお歳暮に対する考え方などは違うので、必ずしもこれが正解というやり方ではありませんが、我が家がどんな感じでやめたかを紹介します。
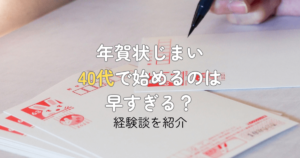
お中元やお歳暮のやめどき

我が家は両家の実家、祖父母宅、付き合いのある親戚にお中元とお歳暮を贈っていました。
双方の祖母がしきたりに厳しい人で、お歳暮を贈らずにいたら叱られたからです。
共稼ぎだったときはあまり感じませんでしたが、子どもが生まれて一馬力になってからは金銭的な負担が大きかったです。
それに毎年何を贈ろうか頭を悩ませており、スーパーやショッピングモールの催事場にギフトコーナーができると、「また今年もこの時期がやってきたのか」とため息を吐いていました。
お中元やお歳暮はそもそも相手への感謝の気持ちを込めた贈り物なのに、面倒に思ってしまうくらいストレスに感じていましたね。
きっと、私と同じような人は多いのではないでしょうか。
義務を感じたらやめる
我が家がお中元とお歳暮をやめたのは、義務でしかなかったからです。
そもそも、両親や祖父母に感謝の気持ちを伝えるのは母の日や父の日、誕生日など他にもあり、お中元やお歳暮に必要性を感じていませんでした。
「去年は油だったから今年は果物でいいか」と選ぶ贈り物に、なんの意味があるのか。
そんな疑問を持ち始めたら、お中元やお歳暮のやめ時なのかもしれません。
年月が過ぎると関係性も変わる
結婚後に贈り始めたお中元やお歳暮も、10年を過ぎると親は60代、祖父母や親戚は60~80代と年月を積み重ねます。
お返しにかかる手間や労力は私たちよりも重い負担となり、ある日、親戚のほうから「今年でやめにしよう」と提案されました。
また、私の祖母が体調を崩し、お世話で直接会う機会が増えたことや、その都度買い出しやちょっとした頼まれ事を引き受けていたので、それで私の気持ちは十分に伝わっているだろうと私自身が思えるようになりました。
一方、旦那方の祖母とはほとんど会わなくなっていたので、お中元やお歳暮を贈らずに文句を言われても、もういいかと開き直れるように。
どちらの祖母も現在は90代となり、お中元やお歳暮に対してあれこれ言われることはなくなっています。
【体験談】我が家のお中元とお歳暮のやめ方

旦那と話し合い、お中元とお歳暮をやめることにしましたが、先方から「やめよう」と言ってくれた親戚を除いて、自分たちが主導になってやめることに少なからず躊躇いがありました。
そこで私たちは、段階を踏んで少しずつフェードアウトしていくことにしました。
まずはお中元をやめる
お中元は上半期のお礼と下半期の健康を願って贈るもの、お歳暮は一年の感謝を伝える締めくくりとして贈るもののため、一般的にはお中元よりもお歳暮が重視されると言われています。
品物の値段も、お中元よりお歳暮を2~3割高く設定するのがよいとされているので、いきなり両方をやめるよりも、お中元のみを最初にやめてみるのがハードルが低いと思いました。
我が家はお中元とお歳暮の両方を贈っていましたが、そもそも必ず両方贈らなけれないけないわけでなく、どちらか一方を贈るならお歳暮のみがよいそうです。
暑中見舞いで挨拶
それまで毎年贈り合ってきたお中元をやめてしまったら、「何かあったのでは?」と相手が心配するかもしれません。
そのときは、時期的に暑中見舞いを出して元気でいることを伝えると、相手も安心できるのではないでしょうか。
品物を贈らず挨拶状だけを送れば、察しよく来年から相手も同じように対応してくれると思います。
続けてお歳暮もやめる
お歳暮はお中元のようにいきなり品物を贈らないのではなく、我が家はさらに段階を踏みました。
相手に「あ、お歳暮もやめたいのだな」と気づいてもらうためです。
金額を下げる
お歳暮にかけていた金額を少しずつ減らしていきました。
お歳暮は必ずしもお返しをする必要はないのですが、毎年お返しを贈ってくれていた親戚は、ある金額に下げた後はお返しを贈って来なくなりました。
もちろん怒ったわけではなく、「お互いのためにもうお歳暮はいいよね」と理解してくれています。
ただし、いきなり大幅に金額を下げるのは相手に対して失礼にあたるため注意も必要です。
気持ちを伝える別の贈り物を用意
年末年始は私の実家に数日寝泊まりさせてもらうので、そのときの滞在費を多めに渡すようにしました。
旦那の実家ではビンゴ大会を行うのが恒例行事となっているので、クリスマスとお歳暮の分を景品代に回す(我が家持ち)という暗黙の了解ですんなりなくなりました。
何を贈ったらいいかわからないお歳暮を選ぶより、確実に相手に気持ちが伝わるものを贈れるのでストレスがありません。
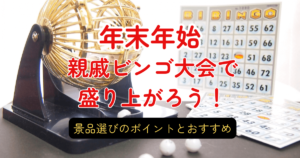
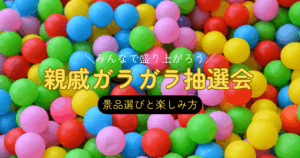
親同士は子ども(私たち)が仲介してやめることに
お中元とお歳暮を贈り合っていた私の実家と旦那の実家(義実家)ですが、母からは毎年「何を贈ればいいのか」相談されていて、どうやら旦那の実家も同じ悩みを抱えているとわかりました。
ということで、私たちが「もういいのでは?」と伝え、お互いの親に子どもを介して「やめにしましょう」と話しをしています。
とはいえ、私たちの親世代であれば、相手から常識がないと思われたくないと、無理やりお中元やお歳暮を贈り続けてしまうケースもあるかもしれません。
一般的には、子どもの結婚後に親同士がお中元やお歳暮を贈り合うのは3~5年が目安とのことなので、このくらいのタイミングでやめても世間的には非常識にはならないと伝えると、やめるタイミングが掴みやすいかもしれません。
まとめ
感謝の気持ちはお中元やお歳暮以外にも伝えることができます。
長く続けてきた習慣をやめるのが難しいのは、誰より惰性であっても続けたほうが楽な自分なのかもしれません。
私はお中元とお歳暮から解放された今、ギフトコーナーの近くを通っても気持ちがざわざわすることがなくなりました。
ブログを読んでくださりありがとうございます。
バナーを押すと、ブログ村の「IN」のランキングに1票が入る仕組みになっています。
応援クリックしていただけると励みになります。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
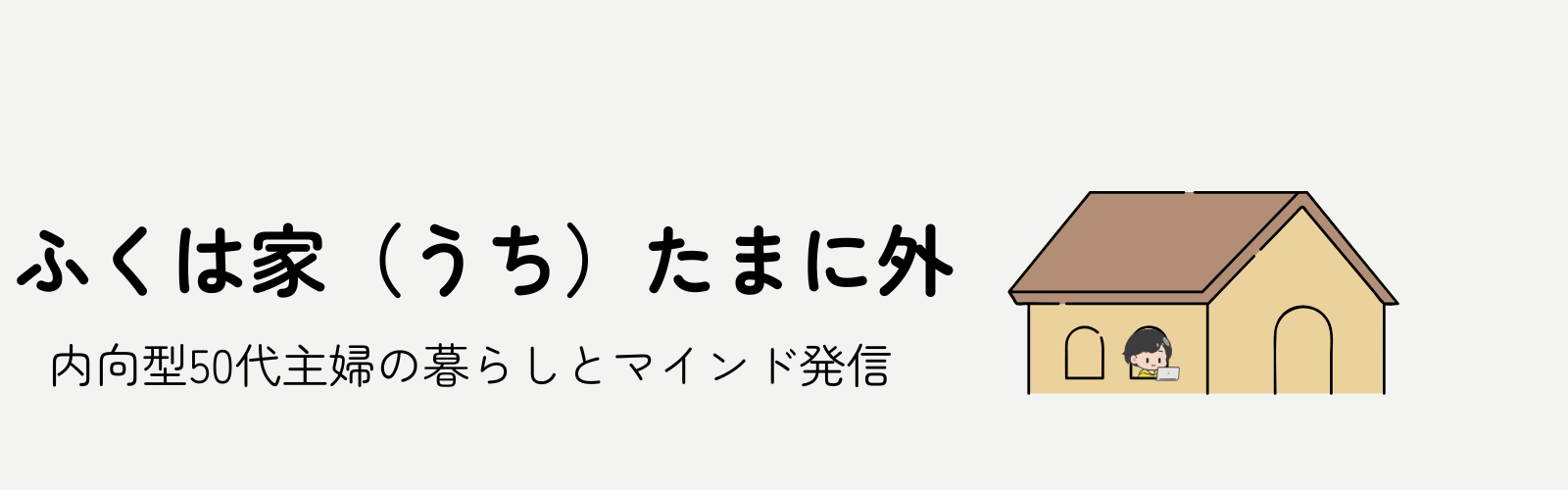
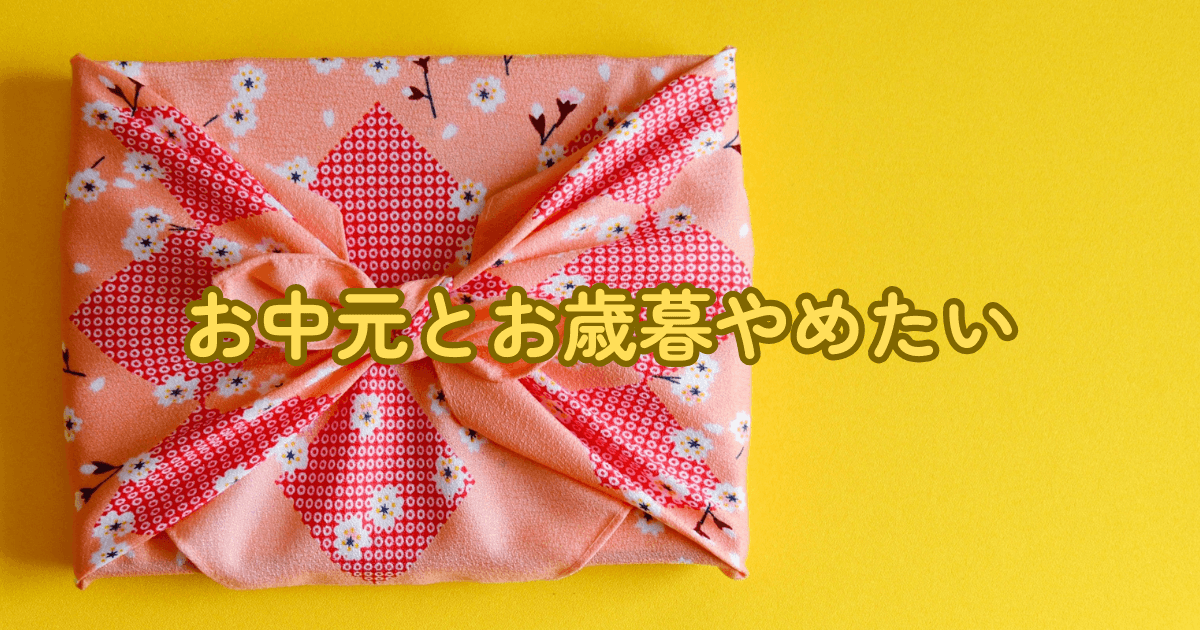
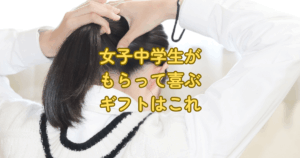
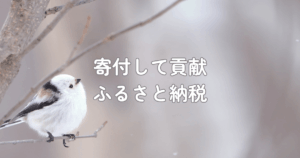

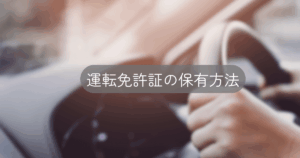
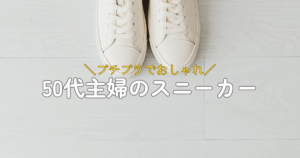



コメント