国民年金の加入自体は申請の必要がなく、20歳の誕生日から2週間程度過ぎると「国民年金加入のお知らせ」が届きます。
今年20歳になった大学生がいるわが家にも、もれなく届きました。
事前に家族で特に話し合いをしていなかったので、「みんなもそうしているから」という子どもに従い、学生のうちは手続きをすれば免除(※)される制度を利用しましたが…
よくよく調べてみると、これでよかったのかという疑問が生まれました。
(※)学生期間の支払いをしなくてよいというわけではなく、追納という形で後から支払うための手続きになります。
学生の国民年金の支払い方法は主に3通り

子どもの国民年金、支払い方法には次の3つがあります。
- 国民年金支払い義務のある本人が払う
- 学生納付特例を利用する
- 親が払う
アルバイトなどで収入があるなど本人が支払う場合は、「国民年金加入のお知らせ」に同封されている「国民年金保険料納付書」を持参して、金融機関や郵便局、コンビニエンスストアで直接支払う他、電子納付(Pay-easy)、スマートフォンアプリの決済、口座振替やクレジットカードでの支払い(口振とクレカ決済は事前の申請・手続きが必要)などから選べます。
とはいえ、多くの場合は学生本人に支払い能力はなく、学生納付特例を利用するか、親が払うかの2択で考えるのではないでしょうか。
冒頭でもお伝えした通り、わが家は学生納付特例を利用しています。
学生納付特例とは?

学生納付特例とは、国民年金機構が実施している制度で、国民年金の支払い義務がある人が学生の場合、申請によって支払いを猶予してもらえるというもの。
猶予期間は最大で10年で、保険料を遡って支払える「追納」が行えます。
厚生労働省「令和5年国民保険被保険者実態調査」によると、学生納付特例を利用している人は 58.2%、納付者は 30.5%、学生特例の申請も納付もしていない人は 7.4%でした。
ただし、利用には学生本人の所得基準があり、118万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等の金額を超える場合は学生納付特例の利用はできません。
たとえば、親の扶養に入ってアルバイトで月8万円収入を得ているといったケースでは、学生納付特例の利用ができるので、多くの場合は利用に問題がないといえるようです。
学生納付特例の申請方法は?
「国民年金加入のお知らせ」に学生納付特例の申請書と返信用封筒が同封されているので、学生納付特例を申請する場合は必要事項を記入して、
- 住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
- 管轄の年金事務所
のどちらかに郵送か、窓口に提出します。
学生納付特例の申請書は、国民年金機構の「ケース12:国民年金保険料の納付猶予を受けるとき(学生の方)」からもダウンロードできます。
または、マイナポータルから電子申請も可能です。
在学中の大学が特例事務法人の指定を受けている場合は、学生課などで申請できます。
対象校は国民年金機構の「学生納付特例対象校」で確認してください。
障害年金の受給資格が得られる
学生時代に国民年金を支払っていない人と、学生納付特例制度を利用した人、どちらも「未納」であるのは変わりませんが、学生納付特例の手続きを行って承認されると、たとえ保険料を支払っていなくても、万が一の事故などで障害を負ってしまったときには障害年金受給の対象になります。
ただし、学生納付特例の承認だけでは受給額には反映されないため、受給額を増やすには追納が必要になります。
受給額には反映されない
65歳に国民保険を満額受け取るためには、20歳~60歳の480カ月、年金保険料を納めていることが条件になります。
学生納付特例を利用すると期間はカウントされますが、受給金額には反映されないので、追納せずに未納期間があると満額はもらえません。
3年度以降の追納は加算額が上乗せされる
また、追納する場合も、猶予から3年度目以降になると「当時の国民保険料(※)+加算額」の支払いとなり、加算額は期間が経過するほど上乗せされます。
加算額は国債の利率に応じているそうで、2023年度までは0.2%だったのが2024年度からは0.6%に上がっています。
2025年に追納する場合の加算額は、調べたところ100円~340円(経過年数に応じる)でした。
仮にわが家が9年間追納を行わず、10年の猶予期間のギリギリ(令和16年度)に慌てて2年分を支払いとなったら、17,510円+340円=17,850×12×2=428,400円を支払うことになります。
加算額がないと2年間の国民年金の支払い額(追納分)は420,240円なので、8,160円加算されることになります。
(※)国民年金料自体は、支払い義務が発生した当時の金額が適用されます。令和7年度の国民年金料は17,510円ですが、令和2年度は16,540円。5年で970円上がっているので、後々に支払うと今払うよりも保険料が高くなるのでは?と心配していましたが、その心配はなさそうです。
追納には割引制度はない
親が支払う方法のところで詳しく紹介していますが、国民年金料を前倒しで払う「前納」には割引制度があります。
後から払う「追納」では2年分まとめて払っても、割引はありません。
10年以内の追納割合は7%
厚生労働省「国民年金保険料の納付猶予制度について」よると、学生納付特例を利用した人が10年以内に追納する割合は1割以下。
9割の人は未納のまま、猶予期間を終えています。
未納の理由はさまざまですが、社会人になって1~2年目に40万円前後の支払いを行うのは、なかなか難しいですよね。
「もう少し貯蓄に余裕が出来たら…」と考えているうち、猶予期間の10年が過ぎてしまい、結局そのままというパターンが多いのではないかと思います。
なお、学生納付特例を利用後、猶予期間内に1年分を追納しなかった場合は老齢基礎年金が年額でおよそ2万円、2年分追納しなかった場合では年額でおよそ4万円が減額されます。
国民年金保険料は20歳~60歳の40年間の支払い期間・額によって、受給金額が決まりますが、60歳以降も厚生年金に加入して働くか、国民年金に任意加入することで満額まで増やすことができます。
毎年申請が必要
学生納付特例の申請は一度きりではなく、毎年4月頃に日本年金機構から届く「国民年金保険料学生納付特例申請について」内のはがきに必要事項を記入して、その都度に申請する必要があります。
たとえば、大学2年生のときに最初の申請をした場合は、大学3年生の4月、大学4年生の4月と、あと2回申請の必要があることになりますね。
親が支払う場合は節税が期待できる

厚生労働省「令和5年国民保険被保険者実態調査」による納付者は 30.5%。
納付者の内訳は公開されていないので、本人と親、どちらが納付したかはわからないのです、おそらくは多くの場合、親が支払っていると思われます。
子どもの国民年金を親が支払っていると聞くと、資金に余裕がある、社会に出る前から借金のようなものを背負わせたくないなど、なんとなく親心なのかなと思ってしまいますよね。
でも、詳しく調べてみると、子どもの国民年金料、親が代わりに払うと節税効果があるとわかりました。
社会保険料控除が受けられる
親が子どもの国民年金を支払った場合、年末調整か確定申告を行うと、市民税・所得税が控除されます。
このとき、同居はもちろんですが、別居でも親が学費や生活費を仕送りしていれば同一生計と見なされるので、社会保険料控除が適用されます。
親の年収などによって税率は変わるという前提で、1年分で約4万円前後の節税効果が見込めるとのこと。
学生納付特例を利用して、本人が就職後に追納をしても社会保険料控除が受けられますが、親が申告したほうが税率が高いので節税効果は高くなります。
本人が毎月支払う、学生納付特例を利用して追納するという方法では、国民年金料は変わりません。
でも、親がまとめて前納すると大きな節税効果が生まれ、2年間分で8万円前後も国民年金料を抑えることができます。
前納割引制度が利用できる
国民年金料の支払いは、毎月納付のほかに6ヵ月前納・1年前納・2年前納が選べます。
前納には割引制度があり、令和7年度は1年分の保険料を現金、またはクレジットカード決済で前納すると3,730円、口座振替で前納すると4,400円の割引が受けられます。
2年分になると現金・クレジットカード決済は15,670円、口座振替は17,010円と1ヵ月分の国民年金料が割引に。
クレジットカード決済は、ポイント還元でさらにお得になりますよね。
社会保険料控除+前納で減る負担額
1年間で5~6万円、2年間で9~10万円ほど負担を減らせる計算です。
約420,000円の国民年金料を、実質320,000円~330,000円で納めることができますね。
就職後に本人から返済してもらうという形をとるにしても、親の立て替えで総額を減らしてあげられるので、あえて表面上は親が支払う方法を選択しているケースもあるようです。
おわりに
学生のときは国民年金の支払いを猶予しますよ~という学生納付特例。
学費や生活費に奔走する親にはありがたい制度ではあるものの、子どもが就職後に自分で支払えばよいと考えるのは、追納の割合を見たら安易すぎるかも…と反省しました。
わが家も2025年度分は学生納付特例の利用を申請しましたが、2026年度・2027年度の分は親が立て替えて後に返済してもらうなど、さまざまな方法を子どもとしっかり話し合い、決めたいと思います。
ちなみに…私自身は20歳時の国民年金を親が立て替え→就職後返済、旦那は学生納付特例を利用して猶予期間ギリギリまで放置→結婚前に督促状が届いて私が慌てて支払うという経緯を辿っております。参考までに。
ブログを読んでくださりありがとうございます。
バナーを押すと、ブログ村の「IN」のランキングに1票が入る仕組みになっています。
応援クリックしていただけると励みになります。
にほんブログ村
にほんブログ村
にほんブログ村
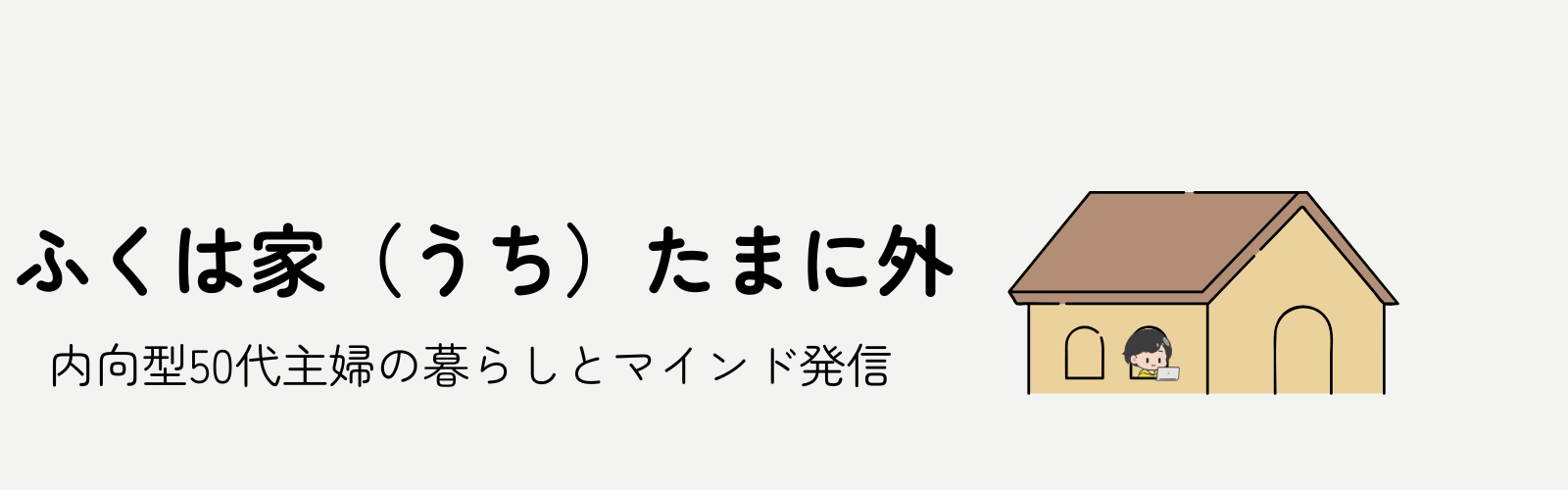
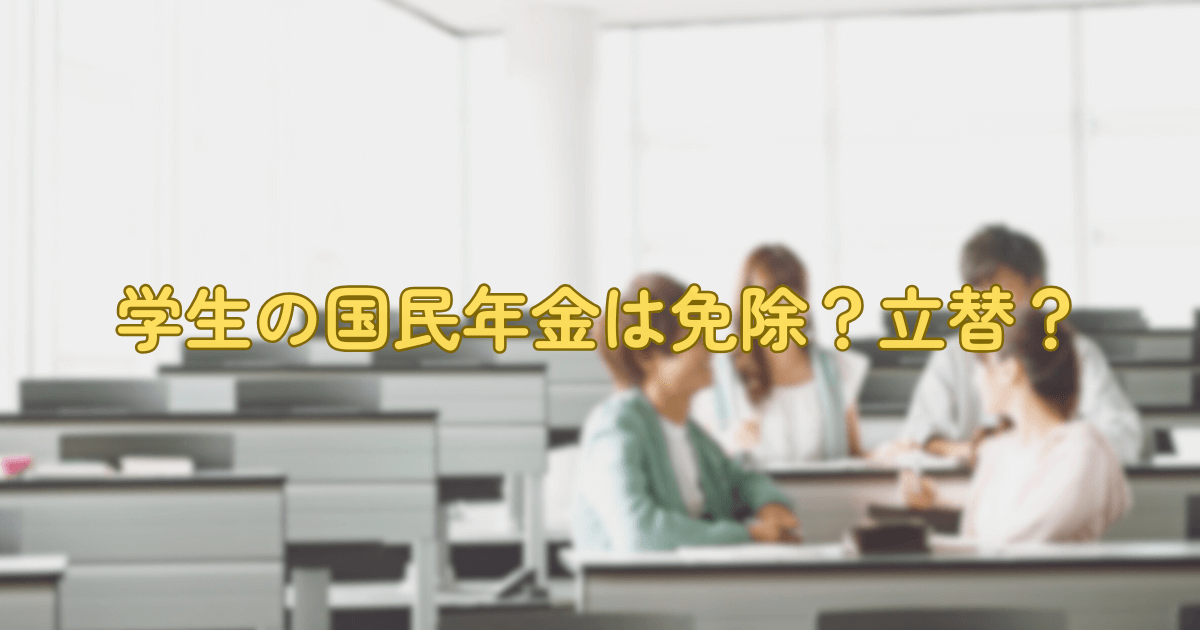

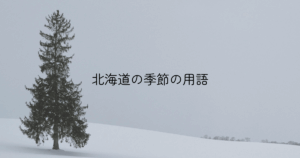
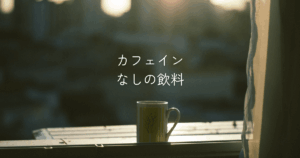
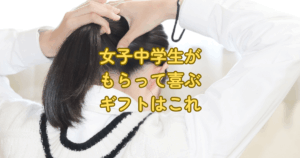
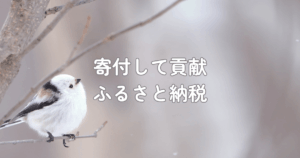

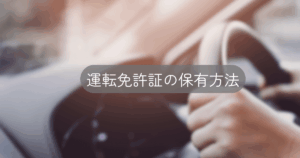
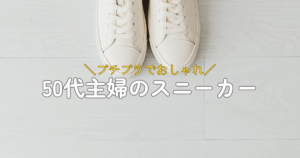
コメント